人材マネジメント論の歴史
川上:今なぜトータルリワードなのか、ということを理解するためには、人材マネジメント論の歴史的な流れを押さえておいたほうがよい。35年も人事コンサルをやってきて、天海和尚張りに私自身が人事の歴史みたいになってしまった(笑)。
【図表】人材マネジメント論の変化
| 時 期 | 考え方 | 説 明 |
| 80年~90年 | HR 人的資源 | 人材は、組織が決めた方向性、プロセスを確実にまわすための資源。決められた方向によく燃えてくれる「燃焼効率のよい人材」が理想。 |
| 90年代~2000年代 | HC 人的資本 | 人材は、組織にとって投資対象。少ない投資で多くの回収ができる「投資対効果」が高い人材が理想。 |
| 2010年以降 | TM タレントマネジメント | 人材は、組織にとって探求すべき対象。優秀かどうかなどのレベル概念は関係ないため、理想の人材イメージは存在しない。むしろ、その人材の持つタレントを理想の状態で活用することが焦点。 |
バブルと人的資源論
1980年代が90年代のはじめ、バブル崩壊の頃まで、人材マネジメント論の世界では、人的資源(HR;ヒューマン・リソース)という考え方がメインフレームだった。人的資源という考え方のもとでは、人材は組織が決めている方向・プロセスを確実にまわす資源と位置づけられる。80年代を振り返ると、仕事のやり方はおおよそ決まっていた。営業はこういう仕事をやる、人事はこういう仕事をやると。決まったやり方を一生懸命やれば成果につながる時代だった。高度経済成長期からバブル崩壊の時期まではそうしたやり方が通用していたのだ。
そこでは、優秀な人材像は、決められた方向によく燃えてくれる「燃焼効率のよい人材」。朝早くから夜遅くまで、「24時間戦える」人間、むちゃくちゃ燃える人間、そういう人たちが優秀とされていて、その代表選手が体育会系の人間で、多くの会社で重宝されていた。もちろん、体育会系がみんなそうとは限らない。単に燃焼効率がよさそうなイメージがあったにすぎないのだが…。ともあれ、そういう人材を採用して、育てようとしていた。
バブルの崩壊と人的資本論
ところが、バブルが崩壊すると、同じ仕事を同じやり方で…ということではうまくいかないようになってきた。もっと独自の考え方をもって自ら動く人が求められるようになってきた。これがバブル崩壊後の90年代だ。そのころに出てきたのが、HC/ヒューマン・キャピタルという考え方。HC=人的資本である。
重要なポイントは、人材を投資の対象として位置づけた点だ。そして、より少ない投資でより多くの回収を得られる人材が優秀な人材であるとして、そういう人材を採用・育成(投資)していこうという考え方に変わったのである。上司が手取り足取り時間をかけて教えなくても、セルフマネジメントで、どんどん自分で成果を生み出してくる。そういう人材は「投資対効果」が高い。上司の投資は少ないのに、回収は多い、投資対効果の高い人材を【ハイパフォーマー】として見出してそれなりのポジションにつけていく(ポジションを与えるのも投資)。高い成果を安定的に、セルフマネジメントで生み出してくるハイパフォーマーに対して、投資対効果の低い人材はローパフォーマーという言葉で呼ばれた。そういう意味では、この当時に成果主義的なやり方が流行したことは納得できるだろう。年齢から職務へという動きもある程度は生じてきた。
本来であれば、この【ハイパフォーマー】に教育の機会を与えよう、報酬も与えよう、もっと投資しようという考えが重要になるはずが、残念なことにそうはならなかった。より少ない投資で回収しよう、というところばかりに焦点が当たってしまったのだ。その結果、ハイパフォーマーは転職してしまうという傾向もあったし、そもそも本当の意味で投資対効果の高い人材が極めて少ないということもわかった。日本の中で人材があまり育っていなかったということがわかってきたのが2000年代以降のことである。
2010年以降のタレントマネジメント
2010年以降、世界の潮流としても同じことが当てはまるが、HR,HCという言葉ではなく、TM=タレントマネジメントという言葉が注目されている。
このタレントマネジメントこそ、トータルリワードの概念が出てきた背景にもなっている。それまでのHC、HRと180度人材の見方が変わっているのだ。何が変わっているのか。それは、理想の人材モデルがないということに尽きる。従来は会社側が理想の人材モデルをある程度持っていて、それをコアバリューに設定して、そのモデルに合うか合わないかで人事評価をしていた。モデルに合わないところがあると育成課題であるといわれてきた。しかし、これはすごく効率が悪い。あるモデルに対してすべて該当する人のほうが少ないのは自明で、1つ合わないだけで評価が下げられてしまうというのは納得感もない。そうしたことの反省から、タレントマネジメントでは「まずモデルを作らない」ということがベースにある。
そもそも1人ひとりの人材はその多寡は問わず、何らかのタレント(才能、能力)をもっている。そのタレントをどう仕事に生かしてもらうことが最も成果につながやすいのか、タレントをどのように組み合わせてチームを作ると最も成果につながりやすいのか、そういったことを考えて人材マネジメントをやっていこうと変わってきた。求める人材のモデルに個々人を当てはめていくのではなく、そもそも個々人に備わっているタレントをうまくマネジメントしていこうという考え方である。
吉本の芸人さんのマネージャーを想像してほしい。担当している芸人がすでに人気で仕事がばんばん入ってくるような超人気芸人ならいざ知らず、すごく有名でもなければめちゃくちゃ面白いわけでもない、人気があるわけでもないといった場合にどうするか。むしろそういうケースのほうが圧倒的に多いだろう。その芸人がどういうイベントにはまるのか、どんなテレビ番組でどんな役割を担わせれば視聴者にウケるのかということを考えて仕事をとってくることになる。人材のマネジメントもそういうイメージに変わってくるということだ。
人材マネジメント論の変化の背景
阿部:このように人材マネジメント論が大きく変わってきた背景はどこにあるのか。そもそも先進国において企業の在り方が変わってきたのか、あるいはその中でも一部の成長企業において成功事例というかたちでそういう考え方が出てきたのか。
川上:両方だと思う。まず変化の最大の原因は、pay for performanceによって社員を動機づけることができなくなってきたことにある。90年代半ばまでには欧米の会社では、pay for performanceで社員を動機づけて成果を回収しようと考えたら相当な金額をインセンティブとして払う必要があり、効率が悪いことがわかってきていた。ちょうどその頃、90年代の半ばに起死回生のいいやり方が見つかった。それがストックオプションだ。会社側ではコストがかからないうえ、億単位の回収も可能。そして動機づけられる。ストックオプションは世界でも日本でも広まった。
けれども、2008年のリーマン・ショックでストックオプションが紙くずになり、下火になった。じゃあどうしようかという試行錯誤のなかで、個々人のタレントが生きるようなマネジメントをやっていこう、個々人が自分の活躍の場を与えられる=やりがいを感じられるような環境を整えていこうという、精神的な報酬の重視という動きが起こってきた。
阿部:役員報酬のコンサルタントとして付け加えさせていただくと、アメリカの会計基準では2000年頃までは、ストックオプションをいくら付与しても全く会社の人件費として、つまり会計費用として計上する必要がなかった。シリコンバレーのテック企業を中心として業績や株価が上がっていく中で、まったくフリーの報酬として便利だった。ただ、それを悪用する人たちが出てきて、エンロン事件、ワールドコム事件が起こった。結局、粉飾をして株価を上げて儲けるというモデルが台頭してきたことで、ストックオプションを会計費用として計上させようという話になって、2000年前半から会計費用の計上が義務づけられた。
そうすると、もはやストックオプションはフリーではなくなる。そうしたうちに、ITバブルの崩壊とかリーマン・ショックという、株価が上がるような状況ではなくなった。そこで、ストックオプションのように株をある価格で購入できる権利ではなく、一定の条件を付した原株をそのまま付与するRSU(リストリクテッド・ストック・ユニット)という報酬に切り替えが進んだ。株価が上がらなくても儲かるからだ。だだし、こうした報酬制度が、今のGAFAMの成長の源泉になっていることは事実で、解説していただいたタレントマネジメントの入口で、つまり人材を採用する時に、原株をサインナップボーナスとして渡すことは非常に多い。まさに人材マネジメント論の変化の裏側で役員報酬もつながっていたことはとても興味深いと思う。(続く)
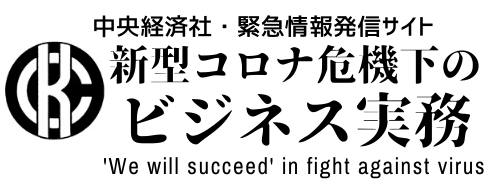
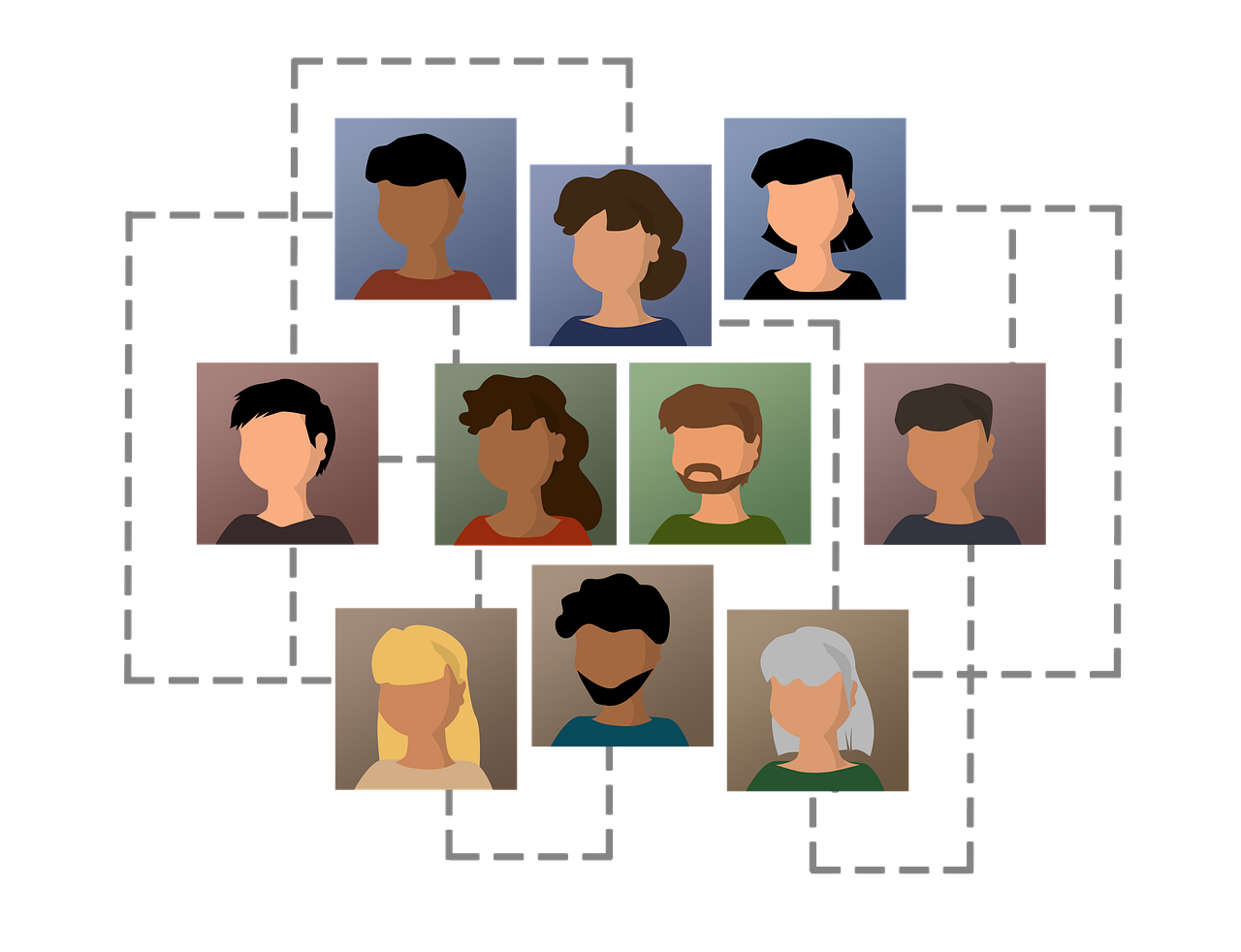


コメント