東京大学教授 清水 剛
先に「感染症と「死」、そして企業経営」というタイトルで戦前の日本の企業経営から「コロナ後」の経営について考える記事を書かせていただいたが、その際には経営といっても、企業の労務管理の側面のみを取り上げていた。そこで、今回は消費者との関係に焦点を当て、「コロナ後」における消費者と企業との関係について考えてみたい。
前回の記事でも述べたように、「コロナ後」の社会は、「死」というものの存在を日常の中に感じるようになった社会、という意味で戦前の日本社会と類似している。それでは、「死」を日常の中で感じる社会における消費者と企業との関係はどのようなものなのだろうか。まず、「死」を感じる社会における消費者と企業の関係を整理した上で、実際に戦前の日本では消費者と企業の関係はどのようなものだったのか、そしてそのことは「コロナ後」の経営にどのような示唆を与えるのかをみてみることにしよう。
「死の影」の下での消費者
「死の影」の下での2つの消費パターン
死を日常的に感じる、という言い回しを何度も用いているとくどいので、ここではいささか文学的だが「死の影」の下にいる、と表現することにしよう(中村真一郎の『死の影の下に』を思いだしてくださっても、堀辰雄『風立ちぬ』の最終章「死のかげの谷」を思いだしてくださってもよい)。
死の影の下にある消費者は一体どのように行動するのだろうか。実は、これには2つの可能性が考えられる。
| ① | 自分の死により家族の収入が途絶える(あるいは死には至らなくても病気により仕事を続けられなくなり、収入が途絶える)可能性を考え、消費を減らして貯蓄を増やす |
| ② | (家族に収入がある場合、あるいは家族がいない場合等家族のことを考えなくてもよい場合には)貯蓄をしても自分が死んだ場合には意味がないので、貯蓄を減らして現在の楽しみのために消費を増やす |
この2つはいささか矛盾するようだが、これは個人や状況によって異なる。端的にいえば、家族がいてその家族の生活を心配するような状況であれば、自分の病気や死のことを考えて節約し、家族の生活を心配しないのであれば、お金を貯めても意味がないのでぱっと使ってしまう、と思ってもらえばよい。
①の場合には貯蓄を増やすために、安さが重要になる。つまり、特定の企業にこだわることなく、安い商品に流れていってしまう。売り手のほうもそのことがわかってくると、低品質の商品を高い価格で売りつける、いわば「ぼったくり」を考えるようになる(このことを顧客も知っていると、そもそも最低品質の商品以外市場取引が成立しなくなる、というのがいわゆる「逆選択」の問題、あるいは「レモン市場」の問題である)。ゆえに、消費者としては、安さを追求しつつ、低品質の商品を避けなくてはいけないことになる。
②の場合には、安さはそこまで重要な問題ではなくなる。しかし、例えば骨董品のようなものを考えてみると、その品質を知ることが容易ではない(下手をすると、買って家に飾っていてもわからない)ために、やはり騙される可能性が高い。
騙されるのを避ける
以上のように考えると、「死の影」の下にある消費者にとっては、何らかの形で騙されることを避けるような仕組みが必要になることがわかる。①と②で消費者の動機はそれぞれに異なり、①の場合には安い価格で生活のための品が一定の品質で供給される仕組みが、②の場合にはぜいたく品や趣味の品について価格は高くてもよいが高品質な品が確実に供給される仕組みが必要となるが、いずれにせよ騙されることを避けることが必要であることは変わらない。
もちろん、騙されるのを避けることは「死の影」の下にない消費者にとっても同じく重要である。しかし、例えば①の消費者を考えてみると、命を失うかもしれない(あるいはそうでなくても病気になるかもしれない)と考える消費者にとっては、貯蓄のために節約するのは切実な課題であっただろう。②の消費者にとっては切実な課題とまではいえないだろうが、しばしば高額な商品であることを考えれば、重要な課題であることには違いない。
それでは、戦前期の日本においては消費者が騙されることを避けるような、売り手からみれば消費者の不安感や不信感を乗り越えるような仕組みはあったのだろうか。次にこの点を、明治期以降の小売業の実態からみていくことにしよう。
戦前の日本における企業と消費者
掛け値、掛け売り、御用聞き
明治維新から大正期に至るまで、小売業は基本的には江戸期から大きく変化していなかったように思われる。すなわち、取引の場においては定価がなく、売り手が自由に値段設定をしていたこと(掛け値)、そして支払いはいわゆるつけ払いで、盆暮れの年2回あるいは月末等に支払っていた(掛け売り)こと、売り手の側で顧客の家を訪問して注文を受け、商品を届けること(御用聞き)が一般的であったこと等の特徴は、江戸から大正に至るまで(そして、さらには昭和に至るまで)維持されていた(廣田誠他『日本商業史―商業・流通の発展プロセスをとらえる』有斐閣, 2017等)。
これらの特徴は売り手に顧客を騙すことを可能にする。まず、現在でも「掛け値なしに」という言葉が、誇張がないことを示す意味で使われるように、掛け値はしばしば高い値段をつけること、言い換えればぼったくりを意味していた。また、御用聞きは顧客にとっては便利である一方で、品物の比較ができないため、低品質の品を売り込んでくる可能性がある。
掛け売りは、それ自体は売り手が顧客を騙すようなものではなく、逆に顧客が逃げる、踏み倒す等の形で売り手に被害を与えることがありうるが、そのような危険性を考えると、取引の際に値段をある程度引き上げておくことが合理的となる。結果的に、掛け売りと掛け値は売り手が顧客を騙す、あるいは騙さなくても若干高値で商品を売ることにつながる。
百貨店の誕生-三越
それでは、このような状況に対してどのような対応がなされたのだろうか。
まず挙げるべきなのは百貨店の誕生だろう。日本で最初の百貨店は三越であるとされる。三越は1904年に三井呉服店の経営を引き継ぐ形で誕生したが、その時点ではまだ百貨店ではなかったといわれる(藤岡里圭『百貨店の生成過程』有斐閣, 2006, pp. 41-42)。とはいえ、すでに品物を店頭に並べて販売する陳列販売や百貨店の1つの特徴とされる定価販売、現金決済も導入されており、また品揃えも拡大して現在の百貨店に近づきつつあった。
この三越のような百貨店はまず上流、中流階級をターゲットとしていたが、これらの人々にとっては、百貨店は高品質の品を豊富に取り揃え、安心して買い物ができる場所であると捉えられていた(初田亨『百貨店の誕生―明治大正昭和の都市文化を演出した百貨店と勧工場の近代史。』三省堂, 1993, pp. 82-86, 94-97)。実際、百貨店は店頭での販売に力を入れる一方で、優良顧客向けの訪問販売(外商と呼ばれる。現在でもいわゆるセレブ向けの商売としてしばしば話題になる)を維持してきた(田村正紀『消費者の歴史―江戸から現代まで』千倉書房, 2011, p. 155)。
さらに、百貨店はこのような上流階級向けのものから、1920年代後半以降大衆化していった(初田前掲, 第6章)。すなわち、1920年代になると上流階級だけでなく、より広く一般大衆にも利用されるようになった。そして、多くの人々にとっては、百貨店とは豊富な品揃えの中で買い物ができるだけでなく、壮麗な建物があり、その中で珍しい催し物や食堂等があるといういわばテーマパーク的な存在であった。
ただし、単にテーマパークであるだけでなく、百貨店は安くて安心して買い物ができる、という認識があることも指摘できる。百貨店について「忙しい時に何でも間に合ひ品物が豊富で、しかも値が安いといふのですから安心して買ふことが出来る」という意見(産婦人科医で教育者の三輪田繁子の意見。大岡聡「昭和戦前・戦時期の百貨店と消費社会」『成城大学経済研究所研究報告』(52), 2009, p.8から再引用)を読むと、特に「値が安い」という部分について若干の違和感を感じるだろう。しかし、上で述べたような掛け売りとしばしば起こる「ぼったくり」の可能性を考えれば、百貨店は「値が安く」て「安心して買ふ」ことができる場所だったのである(ただし、三輪田繁子は三輪田学園の創立者の養子の妻であり、中流以上の階層に属していたことには注意すべきだろう)。
つまり、百貨店というのは②のような消費者に対して高価で高品質な商品を提供するだけでなく、①のような消費者にも一定の品質の商品を供給する仕組みとなっていたのである。関東大震災後に百貨店も一般の人々を対象にして生活必需品の販売を始めたという事実(初田前掲, pp. 177-178)も、こう考えれば理解できるだろう(なお、コロナ禍の中で、百貨店が自主休業を決めた際に経済産業省が「デパ地下」が都心部での食品供給を担っているとして批判し(「『なんて勝手』国が百貨店を非難 デパ地下休業で板挟み」朝日新聞デジタル版2020年4月10日)、ネット上で議論が起こっていたが、この論争の起源はこんなところにある。ただし、現代においては百貨店は主としてぜいたく品を扱っていると理解するのが自然だろう)。
通信販売-主婦之友
しかし、百貨店は数も限られており、行くには時間もお金もかかる。さらに当初は上流・中流階級の人を対象にしていたとなれば、①のような消費者にとって常に利用できる手段ではなかっただろう。
このような場合に利用される手段の1つが通信販売であった。通信販売自体は日本での歴史は長く、明治期の早い段階から存在しており(満薗勇『日本型大衆消費社会への胎動―戦前期日本の通信販売と月賦販売―』東京大学出版会, 2014, p.40)、その後百貨店による通信販売などもみられたが、必ずしも成功したわけではなく、部門も縮小していった。これに対して、通信販売の拡大をもたらしたものの1つが、主婦之友社(現主婦の友社)等の婦人雑誌、あるいは講談社等が設立した「代理部」、すなわち雑誌が商品を紹介し、また生産者に代わって販売する(仲介する)部門であった(前島志保「消費、主婦、モガ―近代的消費文化の誕生と「良い消費者/悪い消費者」の境界について」笠間千浪編『〈悪女〉と〈良女〉の身体表象』青弓社, 2012所収)。
とりわけ、雑誌「主婦之友」の代理部は大きな反響を呼んだ。「主婦之友」は1917年に創刊され、1921年末は販売部数25万5千部に達し、1934年には販売部数100万部に達した、当時最もポピュラーな雑誌の1つである(満薗前掲書, p.193)。「主婦之友」は創刊間もなくして代理部を設立し、家庭のための実用的な商品を販売した。この代理部からは生活に関わる様々な道具や食品(鮭缶等)を販売していたが、滋養強壮剤である「活力素」をはじめとして様々なヒット商品を生んだ。また、1933年頃には編集部が選んだファッションを雑誌で紹介しているうちに、読者からの希望で代理部で販売するようになり、これにも注文が殺到した(主婦の友社『主婦の友社の五十年』主婦の友社, 1967, p.63-65, 154-155, 209. 前島前掲論文)。
このような代理部の販売は、消費者の側からみれば、もともと自分が愛読している雑誌が選んだ商品であるため、雑誌を信用して安心して購入することができる。生産者からすれば、今まで知名度が全くなくても、雑誌が介在することで信用して購入してもらえる。そして、雑誌からみれば、代理部が信用を失うだけでなく雑誌の愛読者が離れるリスクを考えれば、きちんと選んで販売せざるを得ない。
さらに、雑誌という媒体を通じた読者と編集部の強い関係性がこのような販売の仕組みを強化する。上で述べた、雑誌で紹介したファッションを読者の希望で代理部で販売する事例や、読者から募集した図案を審査して優秀作を商品化し、百貨店や代理部で販売して大ヒットとなった「主婦之友浴衣」(1925年から)の事例はこのことを示している(主婦之友社前掲、pp.112-115, 前島前掲論文)。
次頁では、百貨店、通信販売に続き、生協(コープ)が生まれてきた背景をみていく。
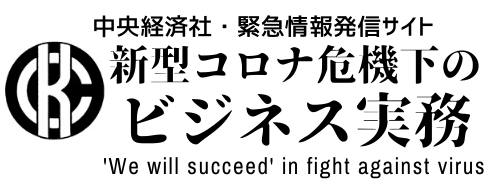




コメント